インタビュー:津谷典子教授
人口データからみる生活と人生のあり方
~現代と近世、時空を超えて人口から社会を研究した津谷教授の軌跡~
~現代と近世、時空を超えて人口から社会を研究した津谷教授の軌跡~

津谷 典子(慶應義塾大学教授)

聞き手:安井 正人(KGRI所長、医学部教授)
少子高齢化が言われて久しい。日本の人口変動を研究してきた津谷典子教授が2020年2月、慶應義塾大学経済学部教授そして経済研究所所長として最終講義を行った。そして、同年4月から、慶應義塾大学教授に就任して新たな活動を始めた。
およそ40年にわたって人口学研究を進めてきた津谷教授の軌跡を辿り、人口変動が社会・経済に対して持つ意味を探る。

「人口学研究」とは
誰でも知っている人口という言葉―しかし人口にまつわる研究がどのようになされているかを知る機会は少ない。
「人口学は、人口を『社会の一部』ととらえ、人口の変動が経済や政治・政策、社会・文化とどういう関係を持つのかを分析する学問です」津谷教授は説明を始める。
「私はその中で、結婚や出生からみた家族形成を中心に研究してきました」
津谷教授は、個人が人生の中で辿るライフコースに着目し、少子化・未婚化の要因や、就学・就業や結婚・出生といったライフイベントのタイミングとイベント間の移行がどのように変化してきたかを探ってきた。
「慶應義塾大学がユニークだったのは、戦前から人口学を基本科目として経済学部のカリキュラムの中に取り込んだこと。1930年代に『人口論』という科目を創設された寺尾琢磨先生(慶應義塾大学名誉教授)の先見の明です」と津谷教授はいう。
人口学は学際的な社会科学の一分野。支える分野は、社会学や経済学、歴史学、疫学や公衆衛生学、数学・統計学など多岐にわたる。
「人口の構造や変化を統計データに基づいて実証分析し、理論を導く、政策立案にも生かすという学問ですので、数理・統計学的な素養も必要です」
インテリではなく大衆のことを知りたい
津谷教授が1980年代にシカゴ大学の博士課程で専門分野として選んだのも、まさに人口統計学と計量分析法だった。
「当時、専門分野を選ぶときに周りを見ていると、経済・社会思想の分野からマックス・ウェーバーやカール・マルクスといったような『崇高なインテリ(high-power intellectual)』の理論・学説を研究対象に選ぶ学生もいた。でも私にとっては、タイプではなかったんです」津谷教授は振り返る。
「私は心底、庶民や大衆(mass)に興味があった。人が何人生まれて、何人死んで、どういう人がどこにいるか、そういうことを知ることが大事だと思いました」
「人口は社会を構成する皆さんのこと。人口統計学は、自分のメンタリティにぴったりフィットしたんです」
「それに人口学は、一人ではできない学問。私でも社会の役に立てるかもと思いました」
人口統計学は、英語でいうと'Demography'。'Demo-'はラテン語で「民衆の」という意味だ。
1990年代に注目を浴び始めた人口学
人口統計分析の研究を始めた津谷教授。
「人口分析法を教えてくださったのが、エヴリン・キタガワ(Evelyn M. Kitagawa)先生。彼女が求める学問の水準(academic quality standard)はとても高いという噂でしたが、みっちりと指導していただき、人口分析について夜中に夢を見るほど必死で勉強しました」
「博士論文執筆中には、各章を一つずつ予め先生に提出し、その後にお会いして、それについてご指導を頂いたのですが、いつも念には念を入れて各章を書き上げ、自信をもって提出したものが真っ赤になって帰ってくる。『ドヒャー!』です。でもその経験を通じて、先生のような一流の研究者としてやっていくためには、どれほど高い水準で、妥協することなく、緊張感を持って研究を続けていかなくてはならないのかを学びました」
1980年代の終わりに津谷教授はアメリカから帰国する。ちょうどそのころ、1990年に『1.57ショック』―前年(1989年)の合計特殊出生率が「ひのえうま」という特殊要因により過去最低であった1966年の1.58を下回ったことが判明した事態―が起こる。
「少子高齢化が言われるようになったのもそのころ。それまでは『学問じゃない』なんて言われていた人口学が、1990年代に入ると、にわかに注目を集めるようになりました。当時は人口学を専門とする研究者も少なく、また女性が珍しかったこともあってか、出生や結婚を研究テーマとしていた私も講演や論文執筆の機会をたくさんいただくようになりました」

江戸時代の人口を調べる
「そんなとき、国立日本文化研究センター教授の故・速水融先生(慶應義塾大学名誉教授)に歴史人口学の大型国際比較研究プロジェクトに参加するよう誘われました。この研究は、ユーラシア5地域における人口・家族構造を比較する国際共同研究プロジェクト(Eurasia Population and Family History Project)の成果である複数の英文図書として結実しました。その結果、人口学者としての私の専門分野は、現代日本をはじめとする先進諸国の出生力と結婚・家族が中心であることに変わりはありませんでしたが、近世日本を中心とした歴史人口についても研究することになり、いわば現代人口と歴史人口の『二足のわらじ』をはくことになりました」
歴史人口学は、近代以前の人口と社会経済について、統計史料を用いてその変動のパターンや要因を実証分析する分野。
分析の対象となる「歴史人口」と「現代人口」の分かれ目は、社会や時代によって違う。
「日本では、1868年に明治維新、そして廃藩置県が1870年ありました。そのころまでがわが国の近世(early modern Japan)にあたり、歴史人口学が扱う時期として誰もがみとめるところです。しかし、わが国で第1回国勢調査(居住する全人口を調査した近代人口センサス)が実施された1920年までの50年間についても、歴史人口学研究の対象と考えていいと思います」と津谷教授は説明する。
近世日本人口、つまり徳川時代の人口は、主に『宗門改帳(しゅうもんあらためちょう)』や『人別改帳(にんべつあらためちょう)』から得られるデータによって把握される。
「宗門改めや人別改めは、町や村が全町村民を対象に定期的に行った人口調査です。宗門改めは当初は隠れキリシタンのあぶり出しのために行われたもので、主に西日本から中部地方および東日本の諸藩で実施されましたが、時間の経過とともに宗教色は失われ、ローカルな人口調査に姿を変えました。一方、人別改めは主に東北地方の町や村で行われた文字通りの人口調査です。つまり、宗門改めや人別改めは、各藩のもとで町や村の政府が行った人口センサスであり、それを記録したものが宗門改帳や人別改帳です」
歴史人口資料からの発見
「私が共同研究者と一緒に行っている歴史人口プロジェクトが主なデータソースとして用いているのは現在の福島県中部、江戸時代の二本松藩の複数の農村の人別改帳で、そこから得られるミクロデータを使って、近世東北農村の人口変動と経済に関する実証研究を約20年にわたり行っています。二本松藩では(徳川時代の宗門・人別改めで圧倒的に多い本籍人口ベースではなく)現住人口ベースで毎年人別改めが行われ、その中でも、1700年代から1870年まで約260年間の記録が殆ど欠年なく残っている3つの農村を中心に研究をしています。これほど長期間にわたり、非常に高い割合で良質な人口史料が残存しているのは稀有なことです。人別改めは世帯単位で実施されているので、各年の記録を連結することにより、世帯とそれを構成する世帯員(個人)のライフコースを再構築することができるのは、素晴らしいことです」と、津谷教授は言う。
これら奥州二本松藩農村の人別改帳には、「各世帯員の名、性別、年齢、戸主との続柄」といった人口史料に通常記載されている情報のみならず、「その世帯が土地をどれほど所有し、耕作し、賃貸借していたか」、さらに「(農耕のための)牛馬を何頭所有していたか」といった経済的な情報も記載されている。さらに、あるお調べから次のお調べの間(1年間)に「生まれたり死んだりした世帯員」についても、「外書き」として朱で記されているという。
「現代人口データは日々アップデートされますが、歴史人口データは何百年も前の人口・社会で起こった事象についての情報ですので、『時代遅れ』になることがありません。歴史人口データを分析することで、人間行動の普遍性が分かると同時に、思いもかけないような新しい発見があります。それが楽しい」
新たな発見の一例として、「人別改帳の出生記載とその出生が記録された年次の世帯員構成から判別される(出生した子の)兄姉の数から分かったこと」を挙げる津谷教授。
「生まれた子供の性比(sex ratio at birth)は、女児100人に対して男児104~107人が生物学的な正常値ですが、二本松藩農村の人別改帳に記録された出生時の性比は全体では106、つまり女児100人に対して男児は106人という正常値でした。しかし、(その子が生まれた年に)生存していた兄姉数別に性比を計算したところ、生存する兄がいない場合には、姉の数がゼロ、1人、2人以上と増えるにしたがって、性比は91、125、205と急増することがわかりました。つまり、息子がおらず娘が二人以上いた場合、記録された出生性比は通常の約2倍(女児100人に対して男児は205人)という高水準であったことになります」
「このことは、限られたリソースのもとで、家族農業の担い手を確保しつつ家系の存続を可能にするために、間引きが広く行われていたことを示唆しています。そしてそれは、凶作や飢饉といった困難時のみならず、平時にも行われていたことがわかりました。つまり、当時の東北農村では、間引きが一種の『家族計画』の手段として用いられ、子供数のみならず出生順位による子供の性別までコントロールしていたと思われます」
一方で、人間行動の普遍性の一例として、津谷教授はこれら二本松藩農村の乳幼児死亡に与える姉の影響が示す家族の絆を挙げる。「江戸時代、東北は稲作の北限であり貧しい地域でした。高い乳幼児死亡率と間引きにより、農村世帯の平均生存子供数はおよそ2~3人でしたが、多くの夫婦は最初は女の子、次に男の子をもつことを目指していたと思われます。そのなかで、生まれた男の子に姉がいると、姉がいない場合に比べて、乳幼児死亡率は有意に低い、つまり男の子が5歳まで生存する確率が大きく増加することが多変量解析によりわかりました。おそらく姉である女の子は(家族農業で忙しい父母に代わって)子守役をつとめ、幼い弟を可愛がって世話していたことが想像されます」
津谷教授はこうした近世東北日本の人口再生産と家族形成について、同時期の東北中国、イタリア北部、スウェーデン南部、ベルギー東部という4つのユーラシア社会を比較分析研究した書籍『Prudence and Pressure: Reproduction and Human Agency in Europe and Asia, 1700-1900』(2010年 MIT Press)で、2012年に日本人口学会賞を、そして2014年には慶應義塾賞を受賞した。1990年代に国際比較研究を始めてから、実に20年ちかくの年月が経っていた。

人口学はどう変わっていくのか
「歴史人口学は、本を一冊出すのに10年かそれ以上かかるような根気を必要とする学問分野です」と津谷教授。
「データ分析に時間がかかり、原史料収集の苦労も多いので、歴史人口学を専門にする学生の数は多くありません。特に近年は、コンピュータと分析ソフトウェアの発達に加えて、大規模調査のミクロデータが容易に入手できるようになったことで、『完成度は低くてもかまわないから手っ取り早く結果を出す研究(quick and dirty job)』をする学生が多くなっているように感じます。しかし、データ解析で『ゴミを入れると、ゴミしか出てこない(garbage in, garbage out)』という表現があるように、拙速な仕事は研究の質の向上の足かせとなります」
「現代は情報過多の時代であり、簡単かつ迅速に情報が手に入ることで、人間が考えなくなる傾向が強くなってきているように思いますが、それではいけない」と警鐘を鳴らす。
人口学もまた、コンピュータをはじめとするテクノロジーの発展により大きな影響を受けている分野だ。
「大規模なミクロデータの入手が容易になり、ソフトウェアの発達も相まって、複雑な多変量解析が可能になりました。コンピュータはプログラムされた仕事を瞬時に正確無比に行いますが、解析のためのモデルや変数の選定はソフトウェアにはできません」
「解析を行う際に『やってはいけないこと』を判断し、『やること』を決めるのは人間です。技術革新が進めば進むほど、人間の意思決定が重要になってきます。意思決定のためには、分析データだけでなく、研究者自身が積み上げた経験や知識、他の研究者との意見交換や共同研究を通じて培われる広く柔軟な視野が必要になります」
「社会科学の実証研究の対象である私たちの社会は、常に変化しています。ですので、分析の対象は数限りなくありますが、これらは必ずしも正解があるものではないのです」
「わが国の最新の『将来人口推計(population projection)』は2015年から2065年までの50年間をカバーしていますが、それによると、今後わが国の人口減少は加速し、人口の超高齢化は更に進むと予想されます。今後の人口変動の大筋は相当な精度で予測することができ、人口の規模や構造のこれからの変化は、その直接的要因である出生や死亡などの既に起こっている変化から将来投影することで推計できます。したがって、人口減少や高齢化への対応は起こってからでは遅く、出生率や死亡率の低下が始まった初期の段階で対応する必要があります。とはいえ、これは『言うは易く行うは難し』で、人口変動の要因と社会経済へのインパクトについて、より学際的に研究を進めていくことが不可欠だと思います」

津谷教授のこれから
今後、津谷教授は、KGRI上席所員として研究を続ける。KGRIでは『長寿化の下でのライフコースの変化』というテーマで研究プロジェクトを立ち上げた。
「これは長期的な視点から、わが国のライフコースの変化を男女別に分析するプロジェクトです」
「私たちの人生は、生まれる、就学する、就業する、結婚する、子供を産む、退職する、死亡するなど、さまざまな人口イベントにより形作られます。そして、これらのイベントには発生するタイミングがあり、またひとつのイベントから次のイベントに移行する確率があります。近年わが国では、これらのイベントを経験する確率と平均的なタイミングが大きく変わってきました」
「初婚を例にとると、わが国は『皆婚(universal marriage)』の文化的伝統をもち、1970年代前半までは、女性の8割強が30歳までに、そして男性の9割以上が35歳までに結婚していました。しかし、1970年代半ば以降、未婚者割合は男女ともに急速に増加し、50歳時の未婚者割合により示される生涯未婚率も、1975年には数パーセント(女性は約4%、男性では約2%)であったものが急上昇し、2015年には女性で14%、男性では実に23%となりました。つまり、2015年には50歳の女性の約7人にひとりが、男性では4人にひとりが未婚だということです。この結婚の急激な減少は少子化をもたらしただけでなく、家族をもたない中高年(特に男性)が急増していることを意味しています。わが国の社会制度は殆ど全員が結婚して家庭をもつことを想定して構築されており、生涯未婚率の急増が日本の社会保障・福祉制度に与える影響は深刻です」
結婚をはじめとするライフイベントの経験確率と平均的タイミングの変化や、それにどういう要因が関わっているのか。また、それが社会や経済にどのような影響を与えるのか。津谷教授の研究はつづく。
次世代へのメッセージ
「学生や若い研究者の方には、自分がやりたいこと、やってみたいことを積極的に探してほしいと思います。これをやってみたい、自分の貴重な時間やエネルギーを投資したい、と思えるようなことを見つけてほしい」と津谷教授。
「ただ、物事は思い通りに行かなくて当たり前です。仕事に楽な仕事はありません。こればかりは経験しないと分からないことかもしれませんが、失敗を恐れずに粘り強くチャレンジを続けてほしいと思います」
「最小限のインプット(努力)で最大限のアウトプット(効果)を得ようとするのではなく、あきらめず、根気強く、自分のことにばかり注目しないで客観的に物事を見て、仕事と人生に向き合っていってほしいです」
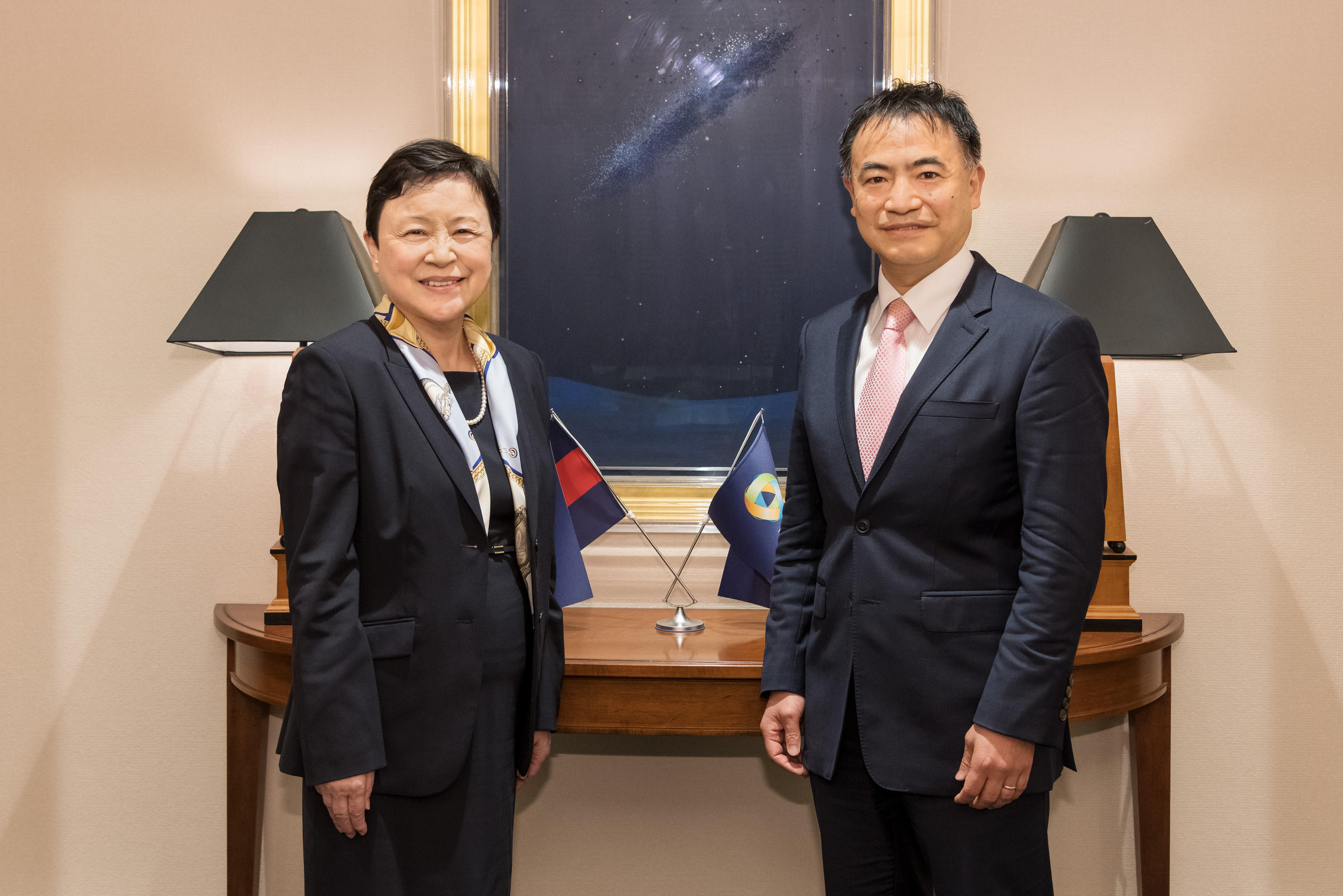
撮影:石戸 晋





