インタビュー:西本祥仁 先生
ユニバーサル対応を可能にする、認知症オンライン診療とAI診断補助技術の研究
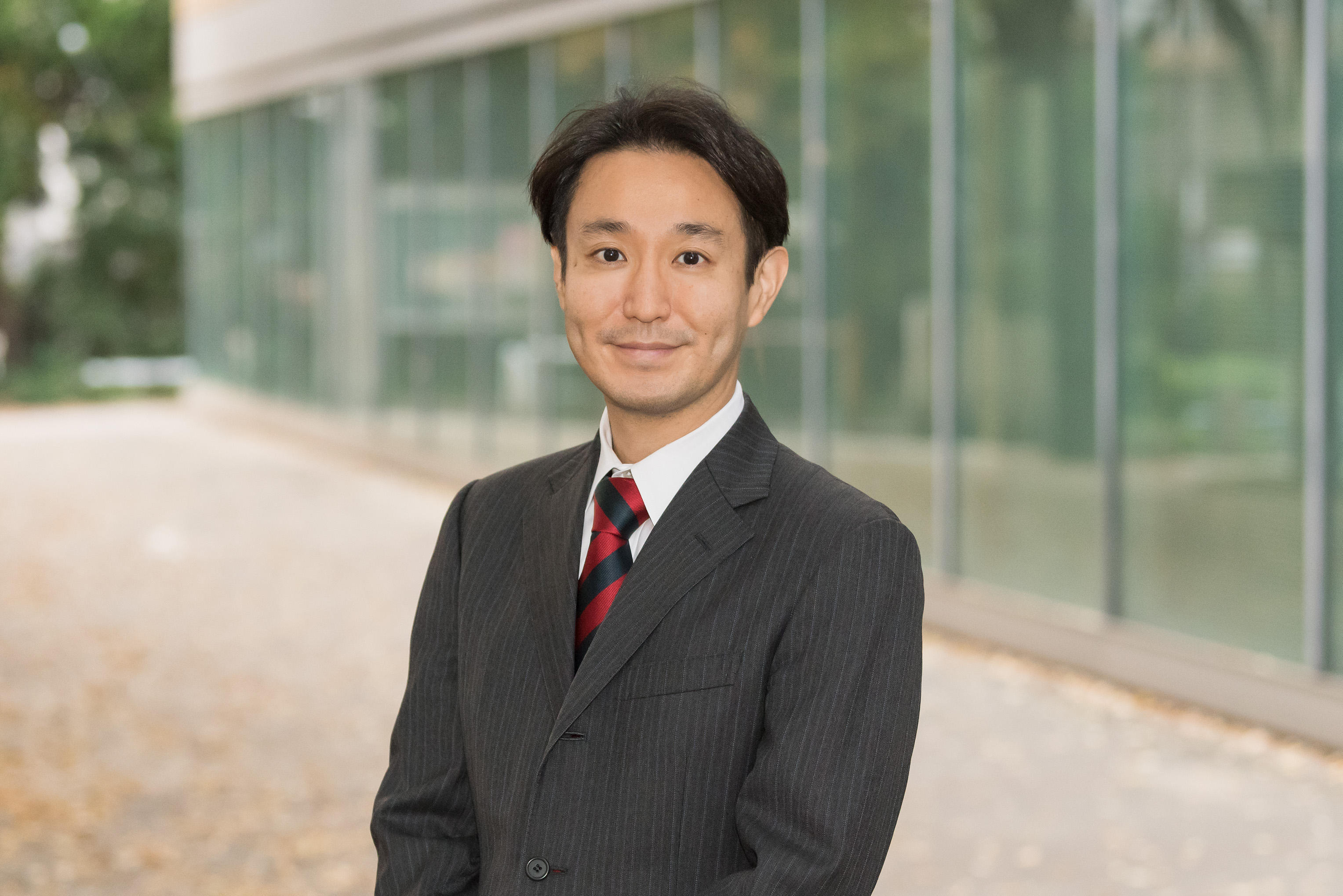
西本 祥仁(医学部内科学教室(神経) 助教)
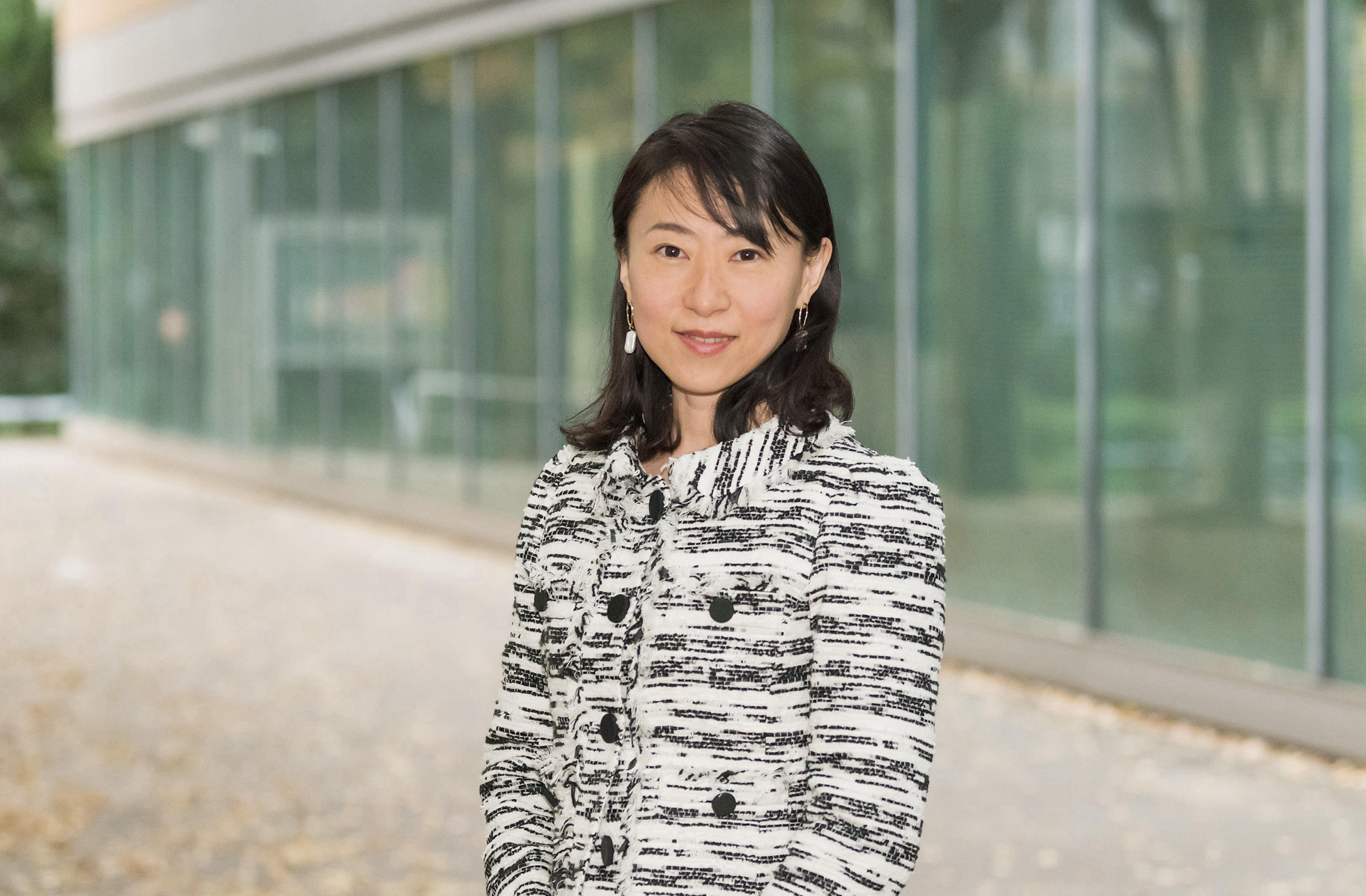
聞き手:鳥谷 真佐子(KGRI 特任教授)
少子高齢化が進む日本で、今後、大勢の人が直面することになる認知症。厚生労働省の推計によれば、2025年には、65歳以上の高齢者のうち5人に1人が認知症患者になると予想されている。さらに2050年には、その数は1000万人規模になるという衝撃の予測もある。そうした事態に備えるため、認知症診断の支援技術の開発や介護者の負担軽減などが重要課題となっている。
そんな中、慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート(KGRI)では、文理融合研究、学問領域横断的研究を推進し、研究成果を世界に還元することで持続可能な地球社会の発展に貢献しようとしている。KGRIスタートアップ研究として、オンライン診療の先にあるAI技術を応用した次世代型認知症診察ツールの開発を進めているのが、慶應義塾大学医学部内科学教室(神経)助教で同大学病院メモリークリニック臨床医の西本祥仁先生だ。
次世代型認知症診療ツールとはどのようなもので、患者やその家族、医療にどのようなメリットをもたらすのか。また本研究が日本社会のみならず、人口の高齢化という共通の課題を抱える世界の国々にどのようなインパクトを与えるのか。西本先生に話を聞いた。

百寿者研究で認知症研究を先導してきた慶應
西本先生は、脳神経内科医として患者を診察しながら研究者でもあるフィジシャン・サイエンティストだ。慶應義塾大学医学部「百寿総合研究センター」では、110歳まで到達するスーパーセンチナリアンを含む百寿者の認知機能評価と全ゲノム配列解析を活用した研究に携わり、現在は慶應大学病院のメモリークリニックで認知症患者の診療にあたっている。「100年以上生きてきた人は認知機能が高く保たれることがわかっており、なぜ認知症になりにくいのか解明する研究を進めています。世界有数の長寿国である日本では、百寿者も急増している。日本は高齢化社会の問題の矢面に立たされている、というニュースがしばしば取り上げられますが、裏返して考えますと加齢に関わる健康問題を解決するには非常に恵まれた研究環境にあると言えます」と西本先生は話す。
もともと慶應義塾大学は、百寿総合研究センターを含む基礎臨床一体型の医学・医療研究体制の構築に力を注いでいる。一方、慶應義塾大学病院では、高齢者人口増加を見据え複数の診療科でオンライン診療の導入が先行して進められていた。認知症専門医であり百寿者の研究経験もある西本先生が、KGRIの後押しを受け、認知症の社会課題解決のためのスタートアップ研究へと進んだのは自然な流れだった。

目指すはユニバーサル・ヘルス・カバレッジの実現
今回のミッションは2つある。認知症の診療にオンライン診療を取り入れることが有用か否かを介護負担の観点から確認すること、そして、患者の音声・画像からAI技術を活用した認知症の診断・病態評価につなげるツールを探索することだ。
「人口の高齢化は世界共通の課題であり、2050年には、認知症の人が世界で1億人以上に達すると言われています。一方で、認知症患者1人を介護するには約3人程度の介護人員が必要とされており、近い将来日本では、数千万人の人がなんらかの形で認知症の介護に関わらなくてはならない時代がやってきます。また、認知症専門医の数は限られており、すべての認知症患者に専門性の高い診療を提供するとなると、認知症専門医一人あたり1000人以上の認知症患者さんを担当する必要が出てくるという計算になります。すべての認知症患者を対象として考えた場合には、医師不足、介護者不足の危機がすぐそこに迫っているとも言えます。
加えて、医療資源の地域格差解消も解決すべき課題の一つです。どれほど専門施設から遠い場所にお住まいでも、患者さんが均質の診察を受けられるように医療提供体制を整備すること、そして、専門医だけでなく一般開業医にも協力して頂き、地域全体で認知症に対して早期からサポート・診療していくことが求められています。本研究は、SDGsの目標でもあるユニバーサル・ヘルス・カバレッジの実現を目指しています」と、西本先生は力を込める。

認知症診療にアクセスしやすい世界を作る
西本先生は、以前から、認知症患者さんの受診に付き添う家族の負担に課題感を抱えていた。認知症がある程度進行している人では、介護者が受診につきそう必要がある。患者は動きが不自由なことも多く、服を選ぶことさえ大仕事だ。家族とヘルパーが協力して外出する準備をし、介護タクシーを予約。病院では車椅子に乗り換え、診察時間を待つ。やっと受診できたところで診療はわずか5分〜15分程度という状況だ。地域に専門医がいなければ、遠方の大きな病院まで足を運ばなければならない。受診の付き添いをはじめ、在宅で見守るにも介護者の負担は肉体的にも、精神的にも非常に大きい。
「付き添いの家族の方と話していると、心の通い合っていた大好きな家族の間でも、介護のつらさから認知症患者さんを疎ましく思う感情が生じてしまう、そして介護者自身がそのような考えを持つこと自体に自責の念を感じる、というケースにしばしば遭遇します。介護負担というのは、人生の中で築き上げてきた関係性まで一気に壊してしまうほどの力がある。このような観点からも、オンライン診療を可能にして、家族の負担を軽減すること、地理的な問題を解決することには大きな意義があると言えます」と西本先生は言う。
研究の前半では、慶應義塾大学病院メモリークリニック受診中の再診患者に対して、従来の対面診療に加え24週間のオンライン診療併用を試みて解析する。コロナ禍で、国のオンライン診療に対する期待感が大きくなってきていることが追い風になっているが、対面診療をオンライン診療に変更したことで、患者さんの認知機能が損なわれるようではいけない。
「本研究を開始するにあたり、メモリークリニックの伊東大介先生がその道筋を切り開いて下さり、プロジェクトの進行においても目標設定と問題点の解決方法を繰り返し話し合ってきました。まずはオンライン診療が、安全に行われることを確認する必要がありました。その上で家族の介護負担軽減にも有効であると示すことができれば、一般診療におけるオンライン診療の有用性が示され、広く普及していくきっかけとなります。遠方の医療機関まで患者さんと介護者が足を運ぶ必要がなくなり、また医師側にとっても、移動先の施設においてでも診察できるというメリットがあります」

これまでの経験から、研究デザインの重要性は身にしみていた。実施にあたっては「クリアしなければならない問題がいくつもあった」と、西本先生は明かす。
「たとえば加齢による物忘れなのか、アルツハイマー型認知症による症状なのか、認知症専門医でも、認知症のごく初期の段階では見分けるのが難しい。今回の対象は『通院できるレベルの認知症』の方。科学的根拠に基づいて患者さんの診断を正確に行い、治験に参加してもらう必要がありました。認知症の中で最も多いアルツハイマー型認知症では、症状が現れる20〜30年も前からアミロイドβという特殊なタンパク質が脳内にたまり始めることがわかっていますので、この病変を正確に捉えることが早期診断につながります。また、もう一つの病態の鍵であるタウというタンパク質の脳内での変化も重要です。慶應大学病院メモリークリニックでは、これらの病態も視野に入れて診察の一助としながら、恵まれた環境の中でスタートを切ることができました」
今回はオンライン診察を行うグループと、来院するグループに分けて比較研究を行っているが、そのグループ分けにも苦慮したという。「年齢や性別をなるべく近づけ、両群の構成患者の背景が偏らないように配慮しています。また今回の研究は仕分けた2群のたすき掛け手法によって、調査の前後半でグループを入れ替える方法をとっています。この方法なら、臨床背景の均一化と十分なデータ数の確保が可能となります」と、西本先生は言う。
遠隔診療の先に狙うは新たな診断手法の開発
本研究の次のステップでは、リモート診療時の音声・体動(頭部振り返り現象)・眼球運動、表情変化のデータ記録にAI技術を応用活用することで、認知症の診断効率向上と、症状の自動評価に役立つシステムづくりを行おうとしている。
「前半の研究結果をもとに、一般診療にオンライン診療が使えるようになれば、同意のもとで生活ログや会話ログなど、認知症患者さんのデータを大量に集められる環境が整います。そして、AIが高い確率で認知症疑いの人の診断をサポートしてくれるようになれば、専門医でなくても簡易的な診察ができるようになります。最終的な診断は専門医が行うにしても、地域のかかりつけ医が診断をする際に補助的なものとして使えるプログラムを作りたい。認知症に関わる地域の人材を増やすことにもつながります」と、西本先生は言う。
神経内科は、診察によって得られる情報に重きを置く科の一つだ。オンライン診療で得る情報を、どこまで対面の診察で得られる情報に近づけられるかは、今後の課題だという。そうした視点が持てるのも、西本先生が臨床医であることが大きい。
「診察室で、我々医師は患者さんが入ってくるときの歩き方や表情、挨拶の声の揺らぎ、匂い、家族の患者に対する接し方まで、五感を使って観察します。つまり、情報を引き出すことが診療の原点とも言えます。一方、オンライン診療では、カメラが向けられている画像と音声による情報だけが頼りです。具体的にどの部分のデータをどのようなアルゴリズムで解析に用いるは、これから選択して準備を進めることになりますが、これまでの経験と知識が活かせると思います」
電話診療とオンライン診療の大きな相違点は、画像情報そのものに加えて、オンライン診療では画像と照合することにより、音声データのどの部分が患者本人のものであるかを切り抜くことができる点にあるという。
「さらに、データが積み上がってくることで、加齢による物忘れとの違いや、認知症を引き起こす様々な疾患ごとの微妙な変化も見えてくるはずです。将来的には、血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症など、アルツハイマー型認知症以外の認知症原因疾患においても早期発見・診断法の解明につながるヒントが見つかるかもしれません。まずは専門医以外の方が活用した場合にAIを介することで〝疑わしい〟例が漏れてしまうことがないように、感度(認知症の人を見逃さない確率)を優先的に維持しながら、特異度(診断精度)を上げていくことをAI技術の目標としたいですね」と、西本先生は期待を寄せる。
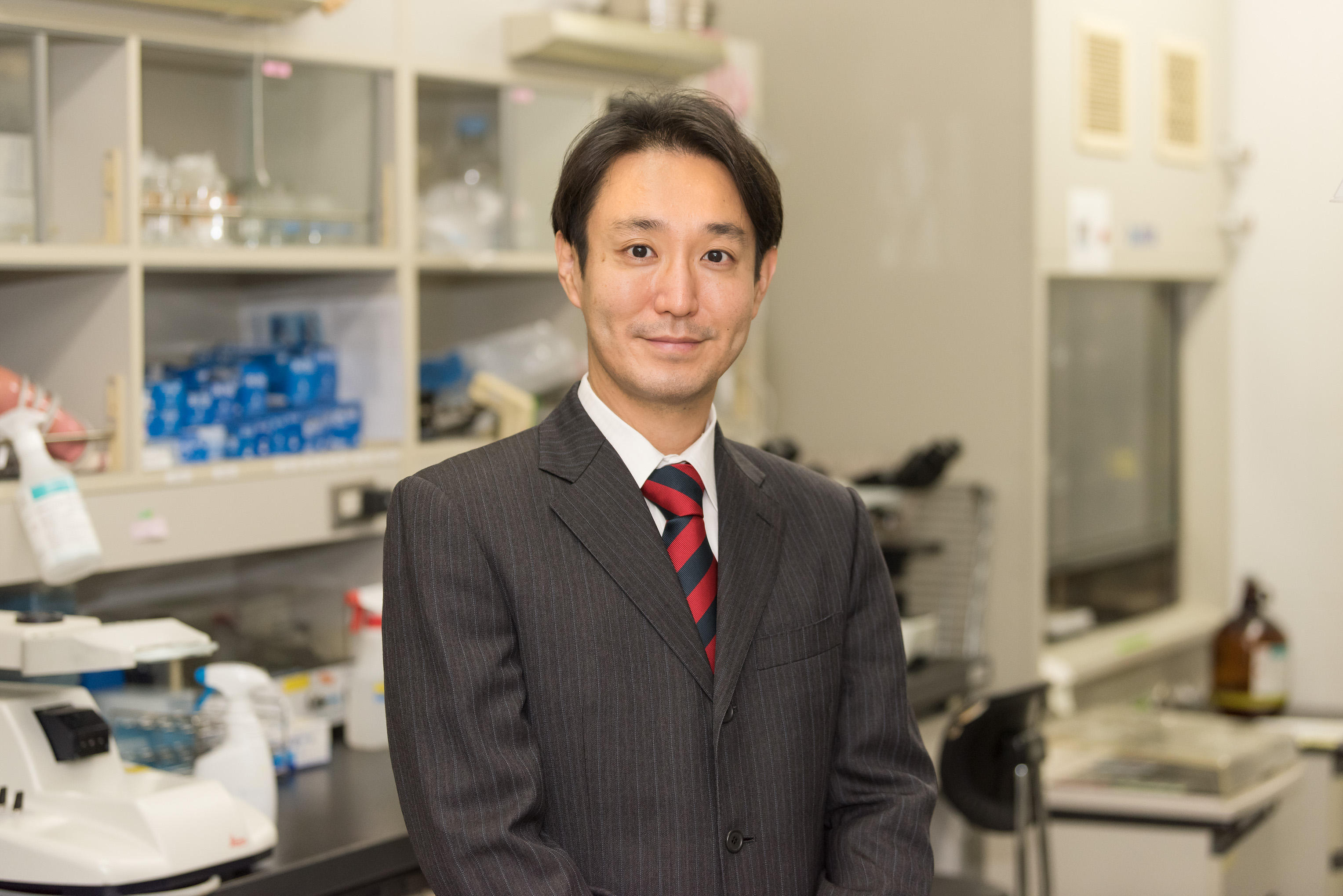
文理融合で社会実装を進めていく
臨床経験から学び得た臨床医としての視点を持ちつつ、研究者としてより精度の高い研究方法を追求していく姿勢は、西本先生だからこそ持てる強みだ。AI診療を〝誰もが使える〟ものにするには、KGRIが掲げる文理融合もカギになる。
「認知症研究は、他の疾患に比べて患者さんの多さが際立っており、日本のみならず、世界に与えるインパクトは非常に大きいものがあります。診断基準や創薬開発のスピードではアメリカがリードしていますが、画像診断技術の応用力や皆保険によって国民全員が均質の医療を享受できるという面は、日本がフロントランナーとして誇れる部分。最終的には日本から世界に還元するまでがミッションだと捉えています。AI診療を現実のものにするためにも、様々な連携をしていきたい。本研究をきっかけに、工学系の方々が参画してくださることを期待しています。科学理論と臨床医学を橋渡しする存在として、社会実装まで道筋を立てていくのも、私の使命かなと考えています」
西本先生が目指す、認知症診断の未来予想図とはどのようなものだろうか
「認知症の克服は世界的な課題であり、治療薬の開発も進められています。世界どこにいても、『この人は認知症の疑いがあるな』というところをAIで捉えることができれば、診療の幅は確実に広がり、医療サービスの公平性にも寄与できるはずです。今後開発されてくる認知症の根本的治療薬は、疾患早期からの導入が期待されると考えています。その時に、完成した慶應発のAI診断補助技術がグローバル展開できていたらうれしいですね」

撮影:石戸 晋





